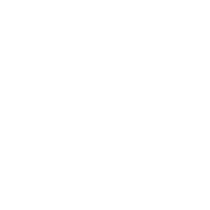海外不動産投資をする際に「為替」の問題は避けて通る事は出来ない。ここでは現在の為替レートを「$=100円」、投資対象の不動産の価格を1000万$(10億円)とし、日本企業(日本人)が直接、海外不動産を取得する「直接投資」の場合を主に考えてみよう。この場合、設立した海外子会社に不動産を取得させる「間接投資」の場合とは、かなり趣きが異なる。
<設例1>として、ドメスティックな事業を展開する会社を想定する。この会社が余資運用としてこの物件を買う時、10億円を1000万$に替えて、この不動産を取得する。
その後、円安になり$=120円になれば、1000万$は10億円から12億円になる。現地での不動産価格の上下とは別に「2億円」の円安による利益が発生するわけだ。
この場合は「外国法人(外国人)が当該不動産の直接的な所有者」となる。不動産収益とは別に投資先の国と日本の税制や市場構造との違いから生ずる節税メリットを狙うことを売り物にしたビジネスも発生、日本の税務当局は先日、これに厳しいスタンスを取るとした。
<設例2>として、輸出業を営む会社を想定する。この会社は受け取ったドル建ての販売代金の全てを円には替えずに一部をドル建ての定期預金として積み立てていたら1000万$となり、これで$=100円の時に不動産を買った。その後、$=120円になったとしよう。
この場合も1000万$の不動産は買った時点では10億円だが、その後の円安で12億円になっている。しかしこの輸出業会社は為替によってもうかったと言えるだろうか?
もし不動産を買っていなければ、この会社には1000万$の預金があったわけで、これを$=120円で換算すれば、やはり12億円である。どちらにしろ、同じように円安メリットを享受できていたのだ。
<設例3>では、新規事業として海外不動産投資を考える会社を想定する。手持ちの円ではなく、1000万$のドル建て借入れを新規に起こして1000万$の不動産を買ったとしよう。ドルで調達してドルの資産を買うので、為替から生じる効果は設例2と同じだ。
ところがことはそうは簡単ではない。「直感」と「会計表現」が異なっているのである。設例3の場合で考えてみよう。
会計で表現する場合、「単純に決算の期末日レートで全ての勘定を円換算する」ことはしない。こう処理していると為替レートの変動でつじつまが合わなくなってしまうからだ。
「流動資産、流動負債」は期末日レート(あるいは当該決算期間中のレート)で円換算し、「固定資産、固定負債」は取得日(年)レートで円換算する、というのが原則である。
しかしこれはこれで妙なことが起こる。
設例3の会社が1000万$(=10億円)を短期借入れで調達し(流動負債)、不動産1000万$(=10億円)を投資用(固定資産)に買ったとする。さきほどの為替換算方法によれば、その後の円安により流動負債の額は12億円に膨らむが、固定資産の額=10億円はそのままだ。負債が増加し資産はそのままなのであるから、差額の2億円は会計的には自己資本の減少、イコール「損失」となってしまう。円高になると逆に「利益」が出る。
ドルの借り入れでドルの資産を買っているので為替の変動による利益や損失は出ていないのに、円建てでの会計上は為替による損益を認識され、それに従った課税がされる。
もし「間接投資」、すなわち海外に設立した子会社で不動産を取得すれば、為替レートの変動に伴う課税上の不測の事態は避けることができる。しかしその場合は日本サイドでは減価償却が取れないなど、不動産投資の節税メリットも放棄することになる。
以上の話は国際税務の入り口のような話だ。この分野は非常に複雑で奥が深く、タックス・ヘブンなどを組み合わせてマニアックなまでに節税を図る企業も出てくる。やりすぎて今、アメリカ政府から厳しく追及されているのが、アップル、グーグル、マイクロソフトなどだ。別のある製造業大手は世界各地でその時々において最善な節税策を繰り返し採用してきた結果、事業の組み替えの際に身動きが取れなくなってしまったと言われている。
私は大昔、先輩がオランダ、ケイマンという2つのタックスヘブンをかませて節税する作業を横で見ていた。当時はまだ国際税務の実務に非常に手間がかかった時代で、また国税局の担当というよりも当時の大蔵省証券局に与える心証が悪く(タックスヘブンに子会社があるというだけの理由で親会社本体の社債発行の審査に影響が出た)、デメリットの方が大きかったという記憶がある。
ジャパン・トランスナショナル 坪田 清
三井不動産リアルティ㈱発行 Realty Press Vol.34 (June 2018)