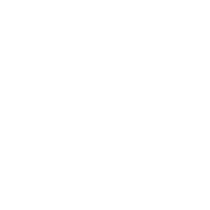お探しのページが見つかりません
ご指定のurlが変更になった、もしくは削除された可能性がございます. ページに戻る
サイトマップ
ブログ
- 2024年01月31日 - デイリー新潮、記事の見出しは「300億円」だが
- 2023年10月16日 - 三井不動産や三菱地所のテレビCMがなぜ時々、超ダサくなるか
- 2023年10月07日 - 東急電鉄へのお願い:「プラレイル」で電車の走り方のパターンを示してほしい
- 2023年09月30日 - 恒大集団の許家印会長が拘束。強制清算となれば「共同富裕」は「共同貧乏」へ転落
- 2023年09月26日 - 「ハーバード大になら75万$(1.1億円)」という大学入学カウンセラーがいる
- 2023年09月09日 - 中国のバブル、土俵際で徳俵に足を載せて踏ん張り、右へ旋回中
- 2023年08月19日 - 「中植企業」、「碧桂園」、「恒大集団」で今度こそ『中国ガラガラポン』の再来か?
- 2023年08月17日 - にわか成金ビリオネア「トム・フォード」が買った大邸宅は、しろうとの投資?
- 2023年08月13日 - 「エクソダスの逆流」は移住したフロリダを去る富裕層から始まる
- 2023年08月12日 - 「碧桂園」でドミノ倒しが始まると中国を超え世界経済を揺るがしかねない
- 2023年07月29日 - アメリカのビル市場、最悪期を脱出した模様
- 2023年07月27日 - ポール・クルーグマン:人口減少下の施策として日本の赤字・巨額財政刺激は「手本」となる
- 2023年07月23日 - 植田総裁、ECBフォーラムで「日銀は (デジタルマネーよりも)まじめに新紙幣を発行する」とする
- 2023年07月16日 - 国家権力が[国家権力を語る詐欺師]を野放し同然にすれば、国家と国民の信頼関係は壊れる
- 2023年07月08日 - 森トラストの大型ビル買収が不調な商業不動産市場の潮目を変える可能性
- 2023年06月29日 - 日本経済新聞・中国総局長のTVでのコメントはここが誤り
- 2023年06月25日 - SREホールディングスの株主総会は去年より上手だったはずだ
- 2023年06月23日 - バカ高い健康・介護保険、「厚労省の歴代課長の名の調査」がつるし上げへの第一歩か
- 2023年06月23日 - 安藤忠雄先生が設計、「安藤伝説」となる予定の超ド級より高い価格の売りが出た
- 2023年06月20日 - 本当の魂胆は「シニアを働かせて税金と保険料をしぼりとろう」
- 2023年06月17日 - 大連万達、香港子会社のIPO許可が得れず資金計画が急転悪化、「恒大集団」の二の舞も起こりうる
- 2023年06月13日 - 安藤忠雄先生設計の豪邸、超ド級の「2億$(280億円)]で成約し安藤伝説が誕生へ
- 2023年06月11日 - 安藤忠雄先生の内部設計マンションが2200万$(31億円)で売りに/原文・無料試読法?
- 2023年05月28日 - 安藤忠雄ファンがカルト的になってコンクリートと先生の哲学をあがめる
- 2023年05月27日 - アメリカのビル不振、注目の「新価格」は従前価格の40-50%引きで始まる
- 2023年05月06日 - ディズニー社とのケンカの下手さで、デサンティス・フロリダ州知事の「大統領の資質」に疑問
- 2023年04月15日 - アメリカの商業不動産の価格下落と商業不動産ローン≒地銀の懸念
- 2023年04月01日 - 「米国不動産の実践豆知識」セミナーでの講演録
- 2023年03月25日 - 対話型AIの「ChatGPT」は不動産ビジネスの実務で即、使える可能性がありそう
- 2023年03月25日 - 中国の一部デベ、デフォルトしたドル建て債のリストラ交渉が前進
- 2023年03月18日 - ソニーや昔の盛田昭夫氏の世界観ってこの程度の物だったのかと言う落胆
- 2023年03月17日 - 海外でトイレ探しで切羽詰まらないための秘訣:ホテルでこの「メモ」を書いてもらう
- 2023年03月04日 - アメリカで「クオリティが高いビル」でもデフォルト等のひび割れが起き始める
- 2023年02月12日 - 安藤忠雄先生が設計した豪邸があるランチが4000万$(53億円)で売れていた
- 2023年02月11日 - ツイッター、サンフランシスコとロンドンで家賃未払いで訴えられる
- 2023年01月29日 - ブラックストーン、今度は機関投資家向けファンドのBPPで問題が表面化
- 2023年01月21日 - 黒田日銀総裁への厳しい批判が始まり、今年は「電気椅子行き」となる見込み
- 2022年12月31日 - 中国のデベの社債(ジャンク債)の価格が突然の急騰、コロナは感染爆発。
- 2022年12月16日 - 長嶋修氏の記事の「アメリカ」の部分はここが大間違い
- 2022年12月10日 - ブラックストーンが不動産ファンドのBREITで償還を制限し、波紋
- 2022年11月28日 - ソニーの不動産子会社・SREホールディングスの今年の宅建士合格率を知りたい
- 2022年11月19日 - 不動産危機対策で中国政府が広範な救済策。これで十分だろうか?
- 2022年11月06日 - bizSPA!の「遠山晃望氏」という方の間取り論は面白い
- 2022年11月05日 - 「アマンレジデンス東京・最上階は300億円か」というデイリー新潮への笑止
- 2022年11月05日 - 若い女性が説明する『デパコメ』と『プチプラ化粧品』の違い
- 2022年10月29日 - 「リモートワーク」がどんなに高く評価されていても、経営者は一貫して疑っていた
- 2022年10月16日 - 若い女性はアパレルを買う前に、想像を超える量と形で情報を仕入れている
- 2022年10月16日 - 若い女性の中には「上着」とは「パーカー」の事だと思っていた人がいた
- 2022年10月15日 - 若い女性のパンプスの鉄板ブランドは「ダイアナ」なのだそうだ
- 2022年10月13日 - 若い女性の中には「パンプスは靴の一種ではない」としていた人もいる
- 2022年10月08日 - リモートワーク礼賛がウソなのを礼賛者は自らが気づいていた
- 2022年09月17日 - 三井不動産の大型ビルを含め、マンハッタンの新築/リノベ物件は好調
- 2022年09月10日 - ブルームバーグの「日本はどうやって交通戦争に勝ったか」
- 2022年09月02日 - 『e-Tax 税務署からのお知らせ』が偽メールではない事はどう確認すればいいのか?
- 2022年08月27日 - アメリカの住宅、売買市場は崩れ始め、賃貸市場はまだ好調
- 2022年08月10日 - 孫CEOの「徳川家康・三方ヶ原の絵」に海外メディアは失笑
- 2022年08月06日 - 習近平氏を「中流層」からも不満の累積が襲う懸念が出る
- 2022年08月06日 - 中国のローン返済拒否、銀行懸念と社会の不満で当局が緊急・絆創膏
- 2022年08月02日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『数学―2』
- 2022年08月02日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『英語―2』
- 2022年08月02日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『現代国語』
- 2022年08月01日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『保健体育』
- 2022年08月01日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『地理』
- 2022年07月30日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『世界史』
- 2022年07月30日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『英語』
- 2022年07月26日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『音楽』
- 2022年07月26日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『日本史』
- 2022年07月25日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『生物』
- 2022年07月25日 - 筑駒(教駒)で私が受けた授業はこんなだった:『数学』
- 2022年07月24日 - 続報:中国でマンションの工事が進まず、購入者たちがローン返済拒否
- 2022年07月16日 - 中国でマンションの工事が進まず、購入者たちがローン返済拒否
- 2022年07月10日 - 米の小売り:売れ筋から外れた大量の在庫や仕入れ、一部は開梱もせずに捨て値で処分
- 2022年07月10日 - 追記:SRE(旧ソニー不動産)のAI価格査定が滅茶苦茶にひどい事がある原因の推測
- 2022年07月07日 - 「筑駒(教駒)」での田植えの日、井の頭線に向って「労組は軟弱だ」とののしった
- 2022年07月05日 - SRE(旧ソニー不動産)のAI価格査定が滅茶苦茶にひどい事がある原因の推測
- 2022年06月26日 - テレ東・相内優香さん、MBA取得との事、おめでとう。
- 2022年06月25日 - マイアミやハンプトンズのホテル室料が50%強、上昇
- 2022年06月13日 - SREホールディングスの株主総会は思ったよりもまともだった
- 2022年06月12日 - ソニーの不動産でのおとり広告はスシローのおとりの20万倍の被害額
- 2022年06月04日 - アマゾン、通販の増加数を過大に見誤り、確保しすぎた倉庫を最大8%削減か
- 2022年05月31日 - 私は横浜銀行を愛するが、本社の指示は支店レベルではここがおかしくなる
- 2022年05月31日 - 「ヒラの身分」では思いつかなかったらしい「ジョブ型雇用」の日本経済へのメリット
- 2022年05月27日 - 課長になれなかった人間がテレビ東京で唱える「ジョブ型雇用」
- 2022年05月14日 - ブラックストーン、新タイプのビークル「BREIT」で不動産投資を拡大
- 2022年05月04日 - ハワイアン航空のフラストレーションがたまっていたパイロット
- 2022年04月23日 - 中国当局が言った「不動産テコ入れ策」がいつまでたっても具体化せず、失望感
- 2022年04月21日 - フロリダでディズニー社、LGTB議論が原因で特権はく奪、年に少なくとも数十億円の損失へ
- 2022年04月11日 - 瑠璃廟(るりちょん)/中国と日本とのとてつもない物価差に幻惑された時代
- 2022年04月02日 - 恒大集団、預金2460億円が簿外債務でおさえられ、投資家は震撼
- 2022年03月27日 - 着陸に成功したら拍手がおきた40年前のネパール航空
- 2022年03月12日 - ウクライナ危機はロンドンのラグジュアリー不動産市場を直撃するだろう
- 2022年03月06日 - ロサンジェルスの575億円の値札だった豪華建売「ザ・ワン」、145億円で落札
- 2022年03月02日 - ディズニー・ワールドの「スタークルーザー」は日本でも大評判になる
- 2022年02月19日 - アメリカで消費や旅行が春以降、爆発的な増加の見込
- 2022年01月29日 - 中国:これほどのリスクをとって投資する魅力はこの国からは薄れた?
- 2022年01月28日 - 中国の不動産危機、日本のバブル崩壊時の邦銀とそっくりな「融資平台(LGFVs)」
- 2022年01月24日 - ソフトバンクへ連続パンチ:クレディスイス訴訟、滴滴出行、アーム、アント汚職
- 2022年01月23日 - 「筑駒(教駒)」では学校の正しい校名を教わっていなかった
- 2022年01月19日 - ソニーがバックにいるのでSREはウソの不動産広告を出しても構わない。ー本気でしょうか。
- 2022年01月16日 - ルーレット必勝法の指南書どおりに賭けたら、勝つべくして勝った
- 2022年01月16日 - マンハッタンで106億円で販売されたマンションが217億円で転売される
- 2022年01月15日 - 香港の歴史的にもアップダウンを繰り返してきた 不動産市場と2021年の様子
- 2022年01月12日 - 建売の共同事業を連立方程式を使って交渉していた時代
- 2022年01月08日 - 昨年、ニューヨークの住宅は売買・賃貸ともに復活し、絶好調だった
- 2021年12月29日 - 「六曜」「寒川神社」「鬼門を否定する論理」が役に立った国内不動産の担当の時代
- 2021年12月28日 - ソフトバンク:滴滴出行株は巨額評価損どころか換金不能になる可能性?
- 2021年12月18日 - オンライン広告の費用対効果が悪化し実店舗の価値の様々が見直される。
- 2021年12月12日 - ソニーグループへの損害請求・20億円?と不動産のメタバース
- 2021年11月27日 - ジロー、アルゴリズムへの自信過剰が主因で巨額の損失
- 2021年11月11日 - 米銀等、オフィスへ復帰しない人間はリストラ対象になりうると暗に脅す
- 2021年11月06日 - フォーシーズンズのナパバレーのホテル、記録的一室単価で売買
- 2021年11月04日 - Caution : Sony’s AI Real Estate Appraisal is Unimaginably Stupid
- 2021年10月31日 - ヒルトン、秒単位のダイナミック・プライシングでインフレに対応へ
- 2021年10月26日 - 小室氏への「満塁ホームラン!」という掛け声は「ホームラン王のナボナ」からと推測
- 2021年10月24日 - 「ソニー」の名に泥をぬる『AI』=おうちダイレクトのAI価格査定は詐欺師に最適?
- 2021年10月16日 - オヨが上場予定。しかしソフトバンクや孫CEOが悪く言われるのは気の毒では?
- 2021年10月09日 - 花様年(Fantasia):恒大集団から飛び火/海外踏み倒しと国内は封じ込め
- 2021年09月30日 - 「ちょんまげの真実」と小室圭氏の勝利と人間としての成長
- 2021年09月25日 - 「ホワイトカラーの低賃金の業務」だけがリモートワークに残るだろう
- 2021年09月11日 - ソニーのゆるふんはアリの一穴へ?:「ソニーグループ共同運営のおうちダイレクト」だと
- 2021年09月04日 - バンクーバーが導入した「空き家税」はうまく機能しなかった
- 2021年08月30日 - 新型コロナで「みんながより豊かになった」というアメリカの意外
- 2021年08月29日 - 恒大集団の破綻処理スキームの理解のために
- 2021年08月19日 - 恒大集団、香港上場親会社とCEOを生贄にして国内金融秩序の維持を図る方向?
- 2021年08月18日 - テレビのコメンテーター出演の要件:高校2年の数学のテストの受験義務付け
- 2021年08月14日 - WeWorkを相手にする大手2社が出現。同社は復活見込みか
- 2021年08月10日 - 恒大集団:中国政府による処分方法が道半ばまで見える
- 2021年07月24日 - マンハッタンでも住宅市場が復活へ。ウルトラ・ラグジュアリーの売買が増加
- 2021年07月18日 - バッハ氏がへつらうヨーロッパ貴族にとって,天皇家は成り上がり国家の土豪か
- 2021年07月15日 - 宿泊希望者が多すぎて大慌てといううれしい悲鳴のAirbnb
- 2021年07月12日 - マイアミの北、サーフサイドのマンション倒壊と「区分所有法」への示唆
- 2021年07月03日 - 世界最大の借金デベ・恒大集団と、デフォルト慣れしてきた中国
- 2021年06月24日 - オリンピック準備の「人流」は「飲み会」よりも大きく、もう始まっている?
- 2021年06月21日 - テレビで横行している「自称・東大生」に、「エセ東大生が混じる」と疑う
- 2021年06月12日 - マンハッタンの超高額マンションが大きく動き出す
- 2021年06月10日 - すごかった三井不動産のCMソング
- 2021年05月27日 - IOCトップへの裏金の可能性は?=オリンピックは「徴兵制」で開催するしかない?
- 2021年05月22日 - 「ハイブリッドな働き方」というシステムは本当に可能なのだろうか?
- 2021年05月15日 - 地下鉄が危険だとして進まないニューヨーカーのオフィス復帰
- 2021年05月06日 - 小室圭氏への集団リンチ:「一字1円か3円」の原稿料でもみんなで全3万ページ?
- 2021年05月01日 - 日本代表たちが自ら参加を辞退することでオリンピックは中止にできる
- 2021年05月01日 - 精査すると「エクソダス(新型肺炎による都市脱出)」は極めて限定的だった
- 2021年04月29日 - 「鈴木光(すずきひかる)」はなんと「女性」だった
- 2021年04月28日 - ニューヨーク:ホテル新築規制と馬車禁止と丸の内のランチ難民
- 2021年04月26日 - ニューヨーク・タイムズにもある、「まるで内容がない記事」
- 2021年04月23日 - 原稿料5万円か10万円程度で小室圭氏への集団リンチに加わる人たち
- 2021年04月21日 - SPACブームに乗り損ねたソフトバンクとWeWork
- 2021年04月12日 - 小室圭氏への集団暴行のメディアとチンピラが、やじ馬たちから冷笑的に見られ始める
- 2021年04月10日 - マンハッタンでは実は7年以上の長期リースの引き合いの方が多いというのが実態
- 2021年04月05日 - 日経電子版、購読止めました(すみません)。
- 2021年04月05日 - 「ジョブ・デスクリプション論者」は恥じいって泥をすするべきだ。世の中はあなた方にはもう甘くはない。
- 2021年04月03日 - みずほ銀行の「ビッグマック指数って何?」という広告への補足と個人的思い出
- 2021年03月31日 - 「在宅勤務を主張する部下」の成績査定を下げるための出題:IRR
- 2021年03月29日 - 「アメリカン・ドリーム」のデフォルトについてJPモルガン他が動く
- 2021年03月23日 - BBCが伝えるイギリスの「返品文化」は異常だし、アメリカはもっと異常なはず
- 2021年03月20日 - ワクチン接種の拡大でアメリカのホテルが回復軌道に入り、稼働率は49%に上昇
- 2021年03月18日 - ソフトバンク:破綻した出資先のグリーンシルと幾重もの不審な関係
- 2021年03月15日 - ソニー必見:「不動産エージェント」ならアメリカでは顧客に何をしてくれるか
- 2021年03月12日 - 住宅ローンと収益物件用のローンに見る日米の違い
- 2021年03月11日 - ソニーが不動産子会社にやらせている「エージェント」のウソと猿まね
- 2021年03月09日 - ソニーが見過ごしている不動産子会社での「おとり」的な行為
- 2021年03月05日 - 都心のオフィス床を減らして出てくるのはジャンクビル並みの床ばかり
- 2021年03月04日 - Airbnbは昨年、超大規模IPOをしたが、話が違う点が幾つかある
- 2021年03月03日 - 後書き・4 外側から見た方が分かりやすいことがある=地球儀のように・・
- 2021年03月02日 - 後書き・3 建築規制を守ればだいたいその通りのものが建つという幸せ
- 2021年03月01日 - 後書き・2 規制そのものはアメリカの方がはるかに厳しい
- 2021年02月28日 - 後書き・1 マネーが東京を嫌うのは規制ではなく規制が読めない為?
- 2021年02月27日 - 前書き・3 中国人のメンタリティは日本人とそっくり
- 2021年02月26日 - 前書き・2 日本の新聞だけがオリンパスの疑惑を報じなかった
- 2021年02月25日 - 前書き・1 日本の新聞は福島での爆発を4行でしか報じなかった
- 2021年02月20日 - ソフトバンクGに『国家反逆罪』で5月の税務申告時から聴取を
- 2021年02月17日 - 「テキサスの賃貸住宅」を投資用に買った方は、ご覚悟を
- 2021年02月17日 - カリフォルニアのナパ・フォーシーズンズ:山火事に懲りない?
- 2021年02月17日 - 「プーチンの宮殿」は、じつはカビだらけだった
- 2021年02月17日 - ホテルのマリオット、カリブ海でポイント消化を狙う顧客もターゲットに
- 2021年02月14日 - 安藤忠雄先生設計の住宅、7500万$(78.8億円)では売れなかった。
- 2021年02月09日 - FTのおかげですごいレベルになってきた日本経済新聞(テレ東)
- 2021年02月06日 - コワーキング各社、新型肺炎で資金的にも絶不調に
- 2021年02月02日 - カルロス・ゴーン事件:これは裁判になじむ話なのか?
- 2021年01月31日 - カルロス・ゴーンが要求した家族旅行の飛行機代の差額
- 2021年01月30日 - ソフトバンクは日本での社会暴動の発生を防ぐためにも、2兆円規模の納税をすべきだ
- 2021年01月26日 - 「メンバーシップ型」「ジョブ型」と語る人たちは、企業でははぐれ鳥?
- 2021年01月21日 - キャノンの業績不振の原因は「家庭用のインク」での儲けすぎ
- 2021年01月17日 - 安藤忠雄先生設計の母屋付きの大牧場が4800万$(49.9億円)前後で成約
- 2021年01月16日 - ブルックフィールド、上場不動産子会社を吸収合併へ
- 2021年01月10日 - ブレジットで「英語」が「EUのラテン語」になる
- 2021年01月10日 - イギリスの住宅市場の現況・・話が滅茶苦茶に複雑に
- 2021年01月09日 - マンハッタンとその周辺の住宅市場の現況
- 2021年01月06日 - 似てきた中国人と日本人の不動産へのメンタリティ
- 2021年01月05日 - 海外から見ると日本の司法制度の乱暴さは中国と大差ない
- 2020年12月26日 - 中国の債務問題、今度はボケた格付け会社から
- 2020年12月23日 - 「ワクシケーション」という旅行業界の新語
- 2020年12月11日 - AIロボットが不動産販売チームの一員に?
- 2020年12月05日 - 不運続きのモール、アメリカンドリームがついに・・
- 2020年11月15日 - メイシーズのパレードは今年はテレビかネットが最高
- 2020年11月14日 - ファイザーのワクチン開発の話で不動産株やリート株が急騰
- 2020年11月07日 - アメリカで最ももうかった不動産投資はたぶん「超豪邸」
- 2020年11月05日 - 「ルーティング」とウォールストリート・ジャーナルの「在宅勤務」
- 2020年11月01日 - 増加しているアメリカの裏口上場(SPAC)
- 2020年10月31日 - 今年のブラックフライデーはわけが分からなくなる
- 2020年10月26日 - 三菱地所が日本一となる超高層ビル・トーチタワーを英語でリリースできなかった理由
- 2020年10月25日 - 竹中平蔵氏には海外資産が300億円あっても不思議はない
- 2020年10月24日 - マンハッタンのオフィスへのスタッフの復帰率は10%
- 2020年10月12日 - イギリスで問題化している「リースホールドの囚人」と上昇する借地料
- 2020年10月09日 - マリオットにみるホテル経営の今後
- 2020年10月07日 - ヨーロッパ最高級ホテルの「ネグレスコ」やパリの「インターコンチネンタル」での体験
- 2020年10月04日 - マンハッタンの不動産市場が非常に急速に悪化
- 2020年10月03日 - スタンプ税の時限的非課税でイギリスの住宅市場は活況に見えるが、長続きはしない?
- 2020年09月23日 - リモートワークを選択した人間は、いずれ組織からはじき出される運命となる
- 2020年09月21日 - オルタナティブ不動産投資/学生寮・自用倉庫・モービルホーム
- 2020年09月12日 - アコーがインターコンの買収を検討
- 2020年08月30日 - アメリカで「ホテルのカラ売り」が始まりそうな気配/CMBX 9とは
- 2020年08月29日 - 安邦保険が韓国のミラエに売ったホテル15棟の所有権の所在の問題
- 2020年08月24日 - 「ソニー」のITのブランド価値を貶め続けている?「旧ソニー不動産」
- 2020年08月22日 - サイモン・プロパティ:モールへのアマゾン誘致と経営不振テナント多数の買収
- 2020年08月15日 - ソフトバンクが絡む先が絡んだ「暗殺と暗殺未遂事件・3件」とウーバーイーツ
- 2020年08月14日 - 就活する女子大生には「紺のリクルートスーツ」を着てもらいたかった理由
- 2020年08月01日 - グロサリーのオンライン販売が大きく伸びたが、配送費負担で利益は伸びていない
- 2020年07月26日 - 「おあいそ」のWebでの説明が「野暮」なのばかりなのか、私が「野暮」なのか
- 2020年07月13日 - ブルームバーグが11分34秒にまとめた「ビジョンファンド」(付記:WeWorkの良いニュース?)
- 2020年07月11日 - ホテルの新しい泊まり方:「ステイケイション」
- 2020年07月06日 - ソフトバンクの孫CEOは一度信じた人をいつまでも信じ続けすぎる
- 2020年07月04日 - ソフトバンクで進行中のスキャンダル3題/ワイアカード、クレディスイス、アーム中国
- 2020年06月27日 - アメリカの「ハンコレス」な不動産取引では・・
- 2020年06月25日 - 生き残っていた「ボストンコンサルティング」と、だんだんずれてきた昨今の私
- 2020年06月21日 - 英字新聞では「ダジャレ」と「韻」にはほとんど違いがない?
- 2020年06月21日 - ワイアカードの巨額資金消失事件にソフトバンクは絡むのか?
- 2020年06月20日 - ロックダウンが緩和されても、オフィスへ完全復帰できるのは驚くほど先に
- 2020年06月15日 - WeWork、奇跡のばん回劇は起こるか?
- 2020年06月15日 - そのまんま東の「検証を」という主張に「どうやって検証するんですか?」と厚労省の技官
- 2020年06月09日 - アメリカでは「在宅勤務からオフィスに戻りたくても戻れる順番がかなり先」という問題
- 2020年06月09日 - 私はこうやってTOEICの点を100点、上昇させた
- 2020年06月08日 - セイコーの中古の腕時計は、昭和の日本の精密機械工業の誇り
- 2020年06月08日 - 効くワクチンもあれば、効かないワクチンもある
- 2020年06月08日 - 最近は聞かなくなった「自宅ころがしで儲けた」という話
- 2020年06月06日 - ウォール・ストリート・ジャーナル、やっと「在宅勤務礼賛」から方向修正か?
- 2020年06月05日 - フィナンシャル・タイムズはそろそろ元のページ数に戻してほしい
- 2020年06月03日 - 「テレワークにより中間管理職が淘汰される」とか「在宅勤務礼賛」というような、あまりに幼稚な説
- 2020年05月30日 - 在宅勤務・リモートワークにはデメリットも多いとアメリカ人たちも気が付く
- 2020年05月27日 - 「マージャンと世論誘導の片棒担ぎ」と「マスク/第二波への対策へのステージ」
- 2020年05月25日 - そのまんま東の限界と橋下徹の鋭さとビートたけしの天才ぶり
- 2020年05月09日 - 三井不動産の「ワークスタイリング」は新型肺炎後のオフィスのモデルの一つに近い
- 2020年05月01日 - 「仮定法」の誤訳が招いた日本の株式市場の総崩れ
- 2020年04月27日 - ますます伸びると見られている「物流倉庫」ビジネス
- 2020年04月26日 - いま、WeWorkをあえて再評価する
- 2020年04月26日 - いま、WeWorkをあえて再評価する
- 2020年04月21日 - 「開成の自由」と「駒場の自由」
- 2020年04月18日 - 新型肺炎の影響が不動産ビジネスの各所に現れ、特に家賃下げと住宅販売に影響
- 2020年04月18日 - 孫CEOのソフトバンク株の担保差し入れ株数の変動とフィナンシャル・タイムズ
- 2020年04月18日 - 孫CEOのソフトバンク株の担保差し入れ株数の変動とフィナンシャル・タイムズ
- 2020年04月10日 - 不動産会社に銀行の役目をしろと言われても無理だ/新型肺炎下でのアメリカの状況
- 2020年04月05日 - ライボーに代わるべき新指標金利SOFRへの移行が進んでいない?
- 2020年04月03日 - ユニゾの経営者に対して取り調べを行うはずの証券取引等監視委員会
- 2020年03月29日 - アメリカのMBS市場が混乱、一部の大型不動産売買が流れた
- 2020年03月29日 - アメリカのMBS市場が混乱、一部の大型不動産売買が流れた
- 2020年03月22日 - 東京ディズニーランドで最も高い土産品は「金色のおみこし・100万円」だった
- 2020年03月21日 - アメリカ、モーゲージ申請は急増したが、新型肺炎で融資実行はべた遅れか
- 2020年03月20日 - ソフトバンクの孫CEOがWeWork元CEOのニューマン氏につけた「いんねん」
- 2020年03月20日 - ソフトバンクの孫CEOがWeWork元CEOのニューマン氏につけた「いんねん」
- 2020年03月18日 - 新型肺炎問題が終息すると、ちょっぴり太めになった美女が世界にたくさん現れるという予想
- 2020年03月12日 - ワン・ワールド・トレードセンターの稼働率が93%となり、合格点にやっと達した。
- 2020年03月07日 - 中国人が国内・海外で住宅購入をパタリとやめるなど、新型肺炎の影響が広まる
- 2020年03月07日 - 中国人が国内・海外で住宅購入をパタリとやめるなど、新型肺炎の影響が広まる
- 2020年03月05日 - 講演料8万円「世界の不動産ビジネス・まんだん」
- 2020年03月04日 - 中国がアヒル10万羽をパキスタンに送って迎え撃とうとしているイナゴの大群
- 2020年03月03日 - 世界で大型不動産等を買いあさっていたHNA(海航集団)が本格的に資金繰りに行き詰った
- 2020年03月02日 - MIPIMについて2年前に報じられた、私は聞いたことがなかった不名誉な話
- 2020年03月01日 - 安藤忠雄先生が設計したカリフォルニアの住宅が7500万$(81.8億円)で売りに出た
- 2020年02月29日 - ウォールストリート・ジャーナルの記事が本当なら、ソフトバンクの携帯電話事業免許は取り消すべきだ
- 2020年02月29日 - ウォールストリート・ジャーナルの記事が本当なら、ソフトバンクの携帯電話事業免許は取り消すべきだ
- 2020年02月27日 - 新型肺炎により中国でもっとも売上げが伸びているのは任天堂のゲーム機のスイッチ
- 2020年02月26日 - 三菱地所の方になぜだか「弟分」として遇されてしまった話
- 2020年02月25日 - 三菱地所との合ハイは成立したことも不思議だが、やはりうまくいかなかった
- 2020年02月23日 - WeWorkに関するフィナンシャル・タイムズの長文記事で意外な点と分かった点
- 2020年02月23日 - WeWorkに関するフィナンシャル・タイムズの長文記事で意外な点と分かった点
- 2020年02月22日 - 「ビクトリアズ・シークレット」で恥をかきそうになった思い出
- 2020年02月20日 - やはり私には無理だった、ブログの毎日更新
- 2020年02月15日 - サイモン・プロパティが同業のトーブマンセンターを36億$(3960億円)で買収
- 2020年02月15日 - サイモン・プロパティが同業のトーブマンセンターを36億$(3960億円)で買収
- 2020年02月11日 - 香港に出現した?秩序崩壊の兆しと、たぶん機能しない香港政庁
- 2020年02月10日 - ソフトバンクの税務申告書には青色申告を認めるべきではない
- 2020年02月10日 - ソフトバンクの税務申告書には青色申告を認めるべきではない
- 2020年02月09日 - 新型肺炎の影響が大きく出ている不動産業の分野はグレイター中国で3つ
- 2020年02月08日 - アメリカの大統領選:民主党の「老・老対決?」とブルームバーグ
- 2020年02月06日 - アメリカ人はいつの時点で選挙の開票作業を続けるモチベーションを失うのか
- 2020年02月05日 - オンライン通販が洗練されていないので日本では百貨店の落ち込みが小さい?
- 2020年02月04日 - ソフトバンクの節税手口を知っても納税意欲を維持している私
- 2020年02月04日 - ソフトバンクの節税手口を知っても納税意欲を維持している私
- 2020年02月03日 - ゴーン氏や伊藤詩織氏の問題で、海外メディアはなぜこう書くのか
- 2020年02月02日 - アメリカ最大の不動産会社は「不動産」を所有していなかった
- 2020年02月01日 - Blackstone Japan Should Master Legendary Dance to Get Unizo’s Deal Done
- 2020年01月31日 - PayPayでやっと解けた謎の一つはどうでもいい事だった
- 2020年01月31日 - PayPayでやっと解けた謎の一つはどうでもいい事だった
- 2020年01月30日 - アメリカ人と宮沢りえにとっての「プール」
- 2020年01月26日 - 「年金値下げの歌」
- 2020年01月25日 - ロンドンで史上最高額の住宅取引。しかしそう認定できるかは不明
- 2020年01月25日 - ロンドンで史上最高額の住宅取引。しかしそう認定できるかは不明
- 2020年01月24日 - 日経電子版の中沢克二記者の書く中国関連の記事は世界最高水準
- 2020年01月23日 - 「世界から日本の不動産を知る・収録コラムの一覧」
- 2020年01月22日 - 「世界から日本の不動産を知る・あとがき」
- 2020年01月21日 - 「世界から日本の不動産を知る・はじめに」
- 2020年01月20日 - BBCの「日本ではなぜ落し物が戻ってくるのか」
- 2020年01月19日 - フィリピンにおける誘拐事件の身代金の今の相場は?
- 2020年01月18日 - アメリカで1億$以上で売買された住宅
- 2020年01月17日 - WeWork問題セミナー(2019年末版)
- 2020年01月17日 - WeWork問題セミナー(2019年末版)
- 2020年01月05日 - 日本の長い正月休みにいらつき始めた海外のメディアとゴーン氏の問題
- 2020年01月04日 - 米のデパート、クリスマス後も大幅値引きを継続し決算が一段と悪化するとの懸念
- 2020年01月04日 - 米のデパート、クリスマス後も大幅値引きを継続し決算が一段と悪化するとの懸念
- 2019年12月14日 - 三菱UFJと三井住友がソフトバンクからの融資打診を断り、距離感に変化
- 2019年12月14日 - 三菱UFJと三井住友がソフトバンクからの融資打診を断り、距離感に変化
- 2019年11月23日 - 三井不動産のハドソンヤードでの投資の成功が確定
- 2019年11月23日 - 三井不動産のハドソンヤードでの投資の成功が確定
- 2019年11月16日 - ソフトバンクに向いかねない日本社会の嫌韓感情
- 2019年11月16日 - ソフトバンクに向いかねない日本社会の嫌韓感情
- 2019年11月05日 - 紅海でサウジの皇太子がソフトバンクの孫CEOに出した警告
- 2019年11月05日 - 紅海でサウジの皇太子がソフトバンクの孫CEOに出した警告
- 2019年11月02日 - 支離滅裂な企業文化で、ソフトバンクと同社のファンドから退職者が相次ぐ
- 2019年11月02日 - 支離滅裂な企業文化で、ソフトバンクと同社のファンドから退職者が相次ぐ
- 2019年10月31日 - 今度こそ、オリンピックを人並みに楽しみたい
- 2019年10月21日 - ソフトバンクは三菱地所のように恥をしのぶべき
- 2019年10月21日 - ソフトバンクは三菱地所のように恥をしのぶべき
- 2019年10月15日 - アメリカ人にとっての中古住宅
- 2019年10月12日 - ソフトバンクの携帯料金はWeWorkの麻薬や乱交だらけのパーティーへも
- 2019年10月12日 - ソフトバンクの携帯料金はWeWorkの麻薬や乱交だらけのパーティーへも
- 2019年10月12日 - ブラックストーンの物流用不動産投資に拍車
- 2019年10月12日 - ブラックストーンの物流用不動産投資に拍車
- 2019年09月30日 - ソフトバンクGの粉飾決算まがい、WeWorkに続き今度はオヨで?
- 2019年09月30日 - ソフトバンクGの粉飾決算まがい、WeWorkに続き今度はオヨで?
- 2019年09月21日 - ソフトバンクの孫氏、WeWorkでアメリカで評判ボロボロ
- 2019年09月21日 - ソフトバンクの孫氏、WeWorkでアメリカで評判ボロボロ
- 2019年08月31日 - ソフトバンクの第二ビジョンファンドに資金集まらず?
- 2019年08月31日 - ソフトバンクの第二ビジョンファンドに資金集まらず?
- 2019年08月24日 - マスコミでは語られていない「バブル」初の消費税と経理マン
- 2019年08月10日 - 無人コンビニのアマゾン・ゴー、ハイテクはともかく客は閑散
- 2019年08月10日 - 無人コンビニのアマゾン・ゴー、ハイテクはともかく客は閑散
- 2019年08月03日 - 昔、「ミッキーは一人」だった
- 2019年07月20日 - ホテルのリゾートフィーについて、ワシントンDCが訴えを起こした
- 2019年07月20日 - ホテルのリゾートフィーについて、ワシントンDCが訴えを起こした
- 2019年06月29日 - 三菱地所、ロックフェラーの名を冠したままアメリカで事業拡大
- 2019年06月29日 - 三菱地所、ロックフェラーの名を冠したままアメリカで事業拡大
- 2019年06月08日 - 「iBuying(住宅即時買取り)によるフリッピング」が拡大している。
- 2019年06月08日 - 「iBuying(住宅即時買取り)によるフリッピング」が拡大している。
- 2019年05月29日 - マスコミでは語られていない「バブル」
- 2019年05月22日 - ソニーが見限ったソニー不動産とその社名変更
- 2019年05月18日 - バンクーバーでの住宅価格高騰にはマネーロンダリングの影響があった。
- 2019年05月18日 - バンクーバーでの住宅価格高騰にはマネーロンダリングの影響があった。
- 2019年05月10日 - 少なくともWeWork株についてソフトバンクGの決算は粉飾まがい?
- 2019年05月10日 - 少なくともWeWork株についてソフトバンクGの決算は粉飾まがい?
- 2019年04月27日 - KKRが日本の大企業傘下の非中核会社をターゲットにする方針を明らかにした
- 2019年04月27日 - KKRが日本の大企業傘下の非中核会社をターゲットにする方針を明らかにした
- 2019年04月21日 - 「神奈川価格」と「東京価格」の断裂線
- 2019年04月06日 - WeWorkの昨年の赤字は一昨年の倍の19.3億$(2160億円)になった
- 2019年04月06日 - WeWorkの昨年の赤字は一昨年の倍の19.3億$(2160億円)になった
- 2019年03月30日 - シアーズの破綻と不動産
- 2019年03月24日 - PayPay はせこく考えると難しい
- 2019年03月24日 - PayPay はせこく考えると難しい
- 2019年03月16日 - 公式オープンを前に、ハドソンヤードが大きく注目された。
- 2019年02月23日 - アマゾンはロングアイランドシティでの巨額の第二本社計画を突然撤回した
- 2019年02月23日 - アマゾンはロングアイランドシティでの巨額の第二本社計画を突然撤回した
- 2019年02月16日 - 日経の海外不動産の記事が随分まともになってきた
- 2019年02月02日 - アメリカのオフィスビル売買市場の先行きについて懸念すべき話が2つ出た。
- 2019年01月27日 - 「オリエンタルランド」という社名を名付けたのは船橋ヘルスセンターの丹澤善利氏
- 2019年01月12日 - アメリカのオフィス賃料は2018年第1-3月期には2.1%上昇に縮小した。
- 2019年01月12日 - アメリカのオフィス賃料は2018年第1-3月期には2.1%上昇に縮小した。
- 2018年12月27日 - いよいよ軟禁覚悟でサウジへ行かざるをえなくなったソフトバンクの孫正義氏
- 2018年12月27日 - いよいよ軟禁覚悟でサウジへ行かざるをえなくなったソフトバンクの孫正義氏
- 2018年12月22日 - 日本の不動産関連が世界の複数の検索等で上位となった。
- 2018年12月22日 - 日本の不動産関連が世界の複数の検索等で上位となった。
- 2018年12月01日 - アメリカの今年のブラックフライデイでは、特にオンライン通販が好調だった。
- 2018年12月01日 - アメリカの今年のブラックフライデイでは、特にオンライン通販が好調だった。
- 2018年11月19日 - ソニー不動産とWeWorkの共通点
- 2018年11月19日 - ソニー不動産とWeWorkの共通点
- 2018年11月10日 - ソフトバンクがサウジ問題で一挙にヒートアップした。
- 2018年11月10日 - ソフトバンクがサウジ問題で一挙にヒートアップした。
- 2018年10月20日 - 中国でマンションの販売事務所に既購入者達が押しかける騒ぎが頻発している。
- 2018年10月20日 - 中国でマンションの販売事務所に既購入者達が押しかける騒ぎが頻発している。
- 2018年10月15日 - 「ソブリン・ウエルス・ファンド」とその奇妙な名前の由来
- 2018年10月14日 - たぶんサウジアラビアで軟禁されることになるソフトバンクの孫正義氏
- 2018年10月14日 - たぶんサウジアラビアで軟禁されることになるソフトバンクの孫正義氏
- 2018年10月07日 - 宅地建物取引士の更新の法定講習の感想
- 2018年09月29日 - シアーズがまた窮地に陥っている。
- 2018年09月29日 - シアーズがまた窮地に陥っている。
- 2018年09月08日 - アメリカの消費回復がしているが、小売り会社の業績は二極化している。
- 2018年09月08日 - アメリカの消費回復がしているが、小売り会社の業績は二極化している。
- 2018年08月27日 - 三井不動産が口火を切った「高級レトルトカレー」という市場
- 2018年08月18日 - ソフトバンクがWeWork(ウィ・ワーク)にまた巨額の資金を投入した。
- 2018年08月18日 - ソフトバンクがWeWork(ウィ・ワーク)にまた巨額の資金を投入した。
- 2018年07月28日 - 巨額の海外M&Aを中国当局から咎められているHNA(海航集団)の共同会長が崖から転落死・・
- 2018年07月07日 - 日本への上陸を狙っているプライベート・エクィティにはブラックストーン、KKR、英ペルミラがある
- 2018年07月07日 - 日本への上陸を狙っているプライベート・エクィティにはブラックストーン、KKR、英ペルミラがある
- 2018年06月16日 - Airbnbは日本で予約を大量にキャンセルするはめになった
- 2018年06月05日 - 海外不動産投資と為替レートの変動と国際税務
- 2018年06月01日 - グローバル不動産経済の本を出します。
- 2018年05月26日 - アメリカで実店舗会社の中に復調を遂げている所が出ている。
- 2018年05月26日 - アメリカで実店舗会社の中に復調を遂げている所が出ている。
- 2018年05月05日 - 英ハマーソンが英のSC会社インツへ出していた・・・
- 2018年05月05日 - 英ハマーソンが英のSC会社インツへ出していた・・・
- 2018年04月13日 - M&Aでは買収の申し入れを受けた側が取る態度が・・
- 2018年04月13日 - M&Aでは買収の申し入れを受けた側が取る態度が・・
- 2018年03月23日 - 世界の住宅市場について興味深い記事が3本出た。・・
- 2018年03月03日 - 海外買収を派手にしすぎた事で監視対象に・・
- 2018年02月20日 - アメリカのマンションなどで起きている「アメニティ・バブル」
- 2018年02月09日 - コワーキングの雄であるWeWorkに対して・・
- 2018年02月09日 - コワーキングの雄であるWeWorkに対して・・
- 2018年01月20日 - アメリカでは法令を満たしているからと言って・・
- 2017年11月05日 - 万科企業を巡る中国初の敵対的買収の顛末
- 2017年08月26日 - アメリカの戸建て住宅レンタルの最大手同士が合併
- 2017年08月07日 - GLPの身売り話、「茶番劇」のシナリオ通りにほぼ決着
- 2017年07月14日 - ヨーロッパで「城」を買う
- 2017年05月07日 - 安邦保険の増資方法はインチキと中国の有力メディアが指摘
- 2017年04月21日 - 急速に拡大したアメリカの一戸建て賃貸住宅ファンド
- 2017年04月13日 - 現在、バブル真っ盛りである世界の諸都市はここ。
- 2017年04月07日 - 極度の経営不振のシアーズ、「最終章へ」と言われ始める
- 2017年03月29日 - 観光客が来るのを有難迷惑?と思っている国(都市)
- 2017年03月22日 - トランプ大統領と不動産関連の話題
- 2017年03月16日 - 中国のCCランドがロンドンの大型ビル、チーズグレイターを買収
- 2017年03月06日 - 好調なアメリカの商業不動産市場に変調の兆し?
- 2017年02月27日 - 海外の高級ホテルの変わったアメニティ
- 2017年02月06日 - ブラックストーン系の一戸建て住宅賃貸最大手が上場
- 2017年01月27日 - 万科企業は敵対的M&Aから逃れた(?)一方、大連万達の不動産売上に異変
- 2017年01月22日 - シンガポールのGLP本体が自身の身売りも含め、検討
- 2017年01月17日 - 今度はムーディーズが巨額和解決着
- 2017年01月06日 - メイシーズとシアーズほかの不振で、あらためて大騒ぎ
- 2016年12月29日 - ドイツ銀行もモーゲージ問題で巨額和解決着
- 2016年12月24日 - ブラックストーン、一戸建て賃貸住宅子会社を上場へ
- 2016年12月20日 - アメリカの今年のブラック・フライデーの注目点
- 2016年12月14日 - サブプライム問題の拡大の裏側と「集団的なモラルハザード」
- 2016年12月06日 - 「天下り先」という観点から見たカジノと統合型リゾートの違い
- 2016年11月28日 - 日本人が刷り込まれていた常識は誤っていた
- 2016年11月21日 - 今度はディズニーにとっての悪い話・2件
- 2016年11月15日 - 上海ディズニーランドの出足、懸念されていたよりも順調
- 2016年11月06日 - 軟化が広がるニューヨークの住宅市場
- 2016年10月26日 - アメリカで近年に勃興した「新しい不動産ビジネス」
- 2016年10月16日 - ちょっと気が早いが、今年の不動産関連M&A・ビッグ3/ヴォノビア・スターウッド・万科企業
- 2016年09月30日 - 「サブプライム・ショック」を振り返る/「サブプライム証券」とは
- 2016年09月23日 - マンハッタンの「ハドソンヤード」
- 2016年09月18日 - Sony’s Real Estate Brokerage Venture Radiates Red With Yahoo!
- 2016年07月26日 - 万科企業vs宝能集団の中国初の敵対的M&Aの死闘も終盤戦?
- 2016年07月22日 - 「国際金融センター」に必要な、ある種のうさん臭さに関する当局からの許容
- 2016年07月17日 - 「愚行」ではなかった、安邦保険のウォルドルフ・アストリアの高値購入
- 2016年07月13日 - マリオットによるスターウッド買収確定までの経緯
- 2016年07月10日 - イギリス:商業不動産ファンドで混乱が止まるわけがない?
- 2016年07月02日 - 日の丸自動車が昔、三井不動産から高く買わされただって?
- 2016年06月27日 - 蓮実重彦先生と同じくらい怖かった大谷幸夫先生
- 2016年06月18日 - 「ソニー不動産」は今年もかなりの赤字か?→経常赤字4.27億円で確定
- 2016年06月11日 - 本格的に割を喰うことになる、50才台中盤以降の「天下り」
- 2016年06月01日 - ソフトバンクは利益を削って、料金値下げとサービス向上に回すべきだ
- 2016年06月01日 - ソフトバンクは利益を削って、料金値下げとサービス向上に回すべきだ
- 2016年04月23日 - 「中森明菜」にさようなら in HDD
- 2016年04月17日 - 春の川越めぐりとお花見の思い出
- 2016年04月07日 - 「東旭川駅」は私にとって十分、「秘境駅」だった
- 2016年03月31日 - 同じくらい重要視されている「住宅価格指数」
- 2016年03月30日 - タロいも畑の売買の決済にも使われていた「ヤップ島の石貨」(4)
- 2016年03月30日 - アメリカで最も重要な住宅統計である「既存住宅販売」
- 2016年03月28日 - dマガジンと相性があうのは、私の場合は「SAPIO」と「サイゾー」
- 2016年03月23日 - 財務省と日本の経済学者を黙らせるためにお越しいただいた?クルーグマン先生ほか
- 2016年03月08日 - 地下鉄サリン事件の日の朝の私
- 2016年03月03日 - タロいも畑の売買の決済にも使われていた「ヤップ島の石貨」(3)
- 2016年02月28日 - ドトールで「チャーシューメン」を注文しそうになった
- 2016年02月23日 - 濱中博久アナはEテレにはめられていた?(ストレッチについて)
- 2016年02月05日 - タロいも畑の売買の決済にも使われていた「ヤップ島の石貨」(2)
- 2016年01月26日 - 定年後もいまだに極端に仲が良い、会社の同期入社の仲間たち
- 2016年01月22日 - タロいも畑の売買の決済にも使われていた「ヤップ島の石貨」(1)
- 2016年01月19日 - 私のテレビ視聴方法。1.4倍速の威力
- 2016年01月12日 - 番組制作予算が急増した? Eテレの「趣味どきっ!百人一首」
- 2016年01月09日 - いまだに正月気分
- 2015年12月31日 - 「差し引けばしあわせ残る年の暮れ」/年越しの失せ物3つ
- 2015年12月27日 - またまたTBSさんに楽しませてもらいました。「伝説の芸能60年史」
- 2015年12月21日 - 私の音楽と貧乏性
- 2015年12月21日 - ニューヨークの「超高額マンション」というセグメント
- 2015年12月20日 - ロンドンの不動産市場は飛び抜けて国際的
- 2015年12月01日 - やはり富山県民は美人だった!!
- 2015年11月22日 - 佐藤養助で稲庭うどんを食べながら話した事
- 2015年11月04日 - 日本橋三越周辺のおすすめレストラン
- 2015年10月24日 - 三囲神社(みめぐりじんじゃ)と三井系の変な施設の思い出
- 2015年10月18日 - 筑波大付属駒場の昔の田んぼ(田植え)の授業 その2
- 2015年10月17日 - 筑波大付属駒場の昔の田んぼ(田植え)の授業 その1
- 2015年10月14日 - 進む私の「IoT」化
- 2015年10月08日 - 私なりに付けたIT各社の「サポート格付け」
- 2015年10月03日 - Apple Watch 到着から137日:時計としての弱点
- 2015年09月29日 - TBSさんのおかげで「『私』の聴きたいラブソング100選」
- 2015年09月25日 - 「楽器挫折者救済合宿」参加報告
- 2015年08月22日 - Apple Watch到着から95日目
- 2015年08月12日 - 「東大合格者数番付上位校」vs「甲子園常連校」
- 2015年08月03日 - NHKのEテレはガチなところが面白い
- 2015年07月30日 - 「群馬のかみなり」と「石垣島のふしぎな雨」
- 2015年07月13日 - 山口百恵菩薩の家の前で手を合わせて
- 2015年07月05日 - 「電話」が昔のパソコンのように使い方が難しくなった時代
- 2015年06月23日 - 「ロンジー」のはきごこちは抜群=これはいい!
- 2015年06月18日 - 伊勢丹MEN’S館にて
- 2015年06月14日 - アップルウォッチ:到着から27日目
- 2015年06月07日 - 文化人類学的発見:日本の新しい「お辞儀」のしかた
- 2015年05月29日 - アップルウオッチの 到着から11日目
- 2015年05月27日 - 最近の若い方は、なぜこんなに感じがいいのか
- 2015年05月25日 - 旅行先で陥ったIT地獄
- 2015年05月25日 - 「吉田拓郎」や「南沙織」は「三橋美智也」になってしまった
- 2015年04月29日 - 半世紀前に「技術・家庭」の授業で作った椅子は、長持ちしていた
- 2015年04月24日 - iTunesはくるくる回らないので直感的にわからない
- 2015年04月17日 - なんとかしてくれ、天丼の金子半之助の行列
- 2015年04月11日 - 東大生活の最初の難関は「うでたてふせ」だった
- 2015年04月06日 - 春の日本橋クルーズと川から見た東京の超高層ビル
- 2015年04月02日 - 「東京ディズニーリゾート」と「ららぽーとTOKYO-BAY」は叔父さんと甥っ子
- 2015年03月29日 - 大昔の三井物産の入社試験のお題は「学歴とはなにか」だった
- 2015年03月26日 - 最近の不動産絡みの大型M&A
- 2015年03月23日 - エームサービスは「エンムサービス」になるところだった
- 2015年03月18日 - 日本橋三越の手芸品売り場は有能すぎる
- 2015年03月11日 - 鈴木ちなみと筑波大付属駒場のカリキュラムの関係
- 2015年03月08日 - 日銀貨幣博物館とヤップ島の石貨
- 2015年03月05日 - NHKの濱中博久アナウンサーは運がいいのか、悪いのか
- 2015年03月01日 - 人前で演奏するのは気持ちがいいが、ギャラはもらえない。
- 2015年02月24日 - 東京国税局の女性職員にはご注意を
- 2015年02月20日 - 定年後は「一日二善」で腹八分目
- 2015年02月17日 - 富山ケンミンは美人だ。新潟ケンミンも美女だが。
- 2015年02月16日 - ネグレスコで教わった「負けようがないルーレットの賭け方」
- 2015年02月15日 - 中森明菜と椿鬼奴とジャパン・トランスナショナル
- 2015年02月14日 - トイレとアメリカン・スタンダード
- 2015年02月12日 - 年金生活に入ると、誰でももう「7万円」欲しくなる。